はじめに
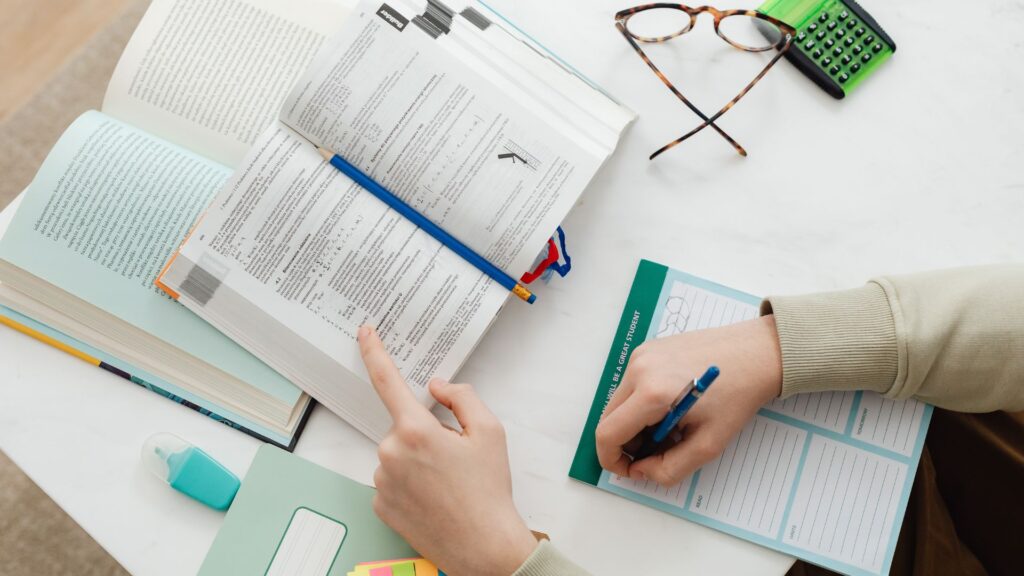
ここでは私が資格取得に動き出すまでを書いていきたいと思います。
今転職を考えている、資格を取ってみよう、スキルアップしたい、と考えいている人たちが
「こんな考え方もある」という一つの参考にしていただけたらと思います。
転職や営業領域へ異動する為に自分に必要と思い勉強して取得した簿記とFPについて、勉強に至る理由やなぜこの資格にしたのかをお伝えしたいと思います。
私が実際に行った具体的な勉強法は別途お話しいたします。
資格を取ろうと思った経緯
転職や部署異動を考え行動に移したとき、私はハッとしました。
今までのキャリアで取ってきた資格は、学生時代に取った教員免許と工場関連のものばかり。もし営業系の仕事に挑戦しようとしたときに、「ビジネスマンとしての武器」がまったくないことに気が付いたのです。
ちょうどその頃、単身赴任が始まりました。平日は家に帰れないので共働きの妻が一人で家事やまだ小さな子ども2人の育児をやってくれていました。そんな状況で自分だけ自由な時間を遊んでいるわけにはいかない、と強く思いました。そこでこのひとりの時間を有効に使うために考えたのは「勉強すること」。そしてどうせなら自分のキャリアに直結する資格を取って、異動や転職の希望に箔をつけよう、と考えたのです。
会社に提出した異動願いも、転職を考えていた企業も営業系だったこともあり、必要だと思ったのは「ビジネスマンとしてのスキル」。そのために、社会人としての教養が身につく資格を取ろうと決めました。
なぜFPと簿記か
「社会人としての教養を身につけたい」と思ったとき、世間でよく見聞きするのが FP(ファイナンシャルプランナー)と簿記 でした。
実際に調べてみると、資格に関するランキング記事やSNSでの投稿でも、この2つは必ずと言っていいほど紹介されています。
- 「社会人なら持っておきたい資格」
- 「転職やキャリアチェンジに役立つ資格」
- 「お金や経理の基礎を理解できる資格」
こういった枕詞とともによく紹介されるのがFPと簿記です。
しかも、どちらも 独学で挑戦しやすい 、そして短期間での取得が可能ということが大きな魅力でした。
たとえば、国家資格であるFP3級は出題範囲が生活に直結しているため、テキストを読み進めれば自然と理解できる内容が多い。2級も合格率はぐっと下がるが独学でもできる情報がある。簿記についても実際のところ、私は通信の教材を取り寄せはしましたが、2級までは市販の参考書や問題集、過去問を中心に学習を重ねれば合格が狙える資格です。
そして、勉強時間も約3か月と紹介されている情報を多く見かけるので短期間での取得が可能と考えました。
私が短期間で資格所得を狙ったのは単身赴任を早く終わらせるために異動や転職をしたかったからで、2年も3年も資格取得に時間を使う気はさらさらありませんでした。
さらに実用性という観点でも非常に優れていると感じました。
- FP:家計、保険、年金、投資、住宅ローンなど「人生とお金」に直結する知識が学べる
- 簿記:会社のお金の流れを理解できるので、営業職やマネジメント職を目指すうえで大きな武器になる
「転職や異動を考えている自分にとって、どちらもキャリアの土台になる」
そう確信できました。
- 独学で取得可能
- 短期間で取得できる
- ビジネスマンとしてのスキルを身に着けキャリアの土台を作る
以上のことが、FPと簿記に挑戦しようと決めた理由です。
そしてキャリアの土台とするにはどちらも2級まで必要と考えましした。
勉強を始める決意

もちろん不安がゼロだったわけではありません。
仕事と勉強を両立できるのか、本当に合格できるのか――頭をよぎった瞬間もありました。
それでも私は「一度やると決めたことは必ずやり切るタイプ」です。今回も「資格を絶対に取る」と心に決めました。決めてしまえば迷いはありません。あとはやるだけ。
単身赴任で時間はある。支えてくれる家族もいる。
資格を取ってキャリアに箔をつけ、早く単身赴任から抜け出そう!
長い期間ずるずるやりたくないので、できるだけ早く両方必ず合格する。
その強い決意でFPと簿記の勉強をスタートさせました。
まとめ
ここまで、私が資格取得に動き出すまでの経緯をお伝えしました。
- 工場系資格しかなく、ビジネスマンとしてのスキル不足を痛感
- 単身赴任を前向きに活かし、「資格取得」という挑戦を選んだ
- 教養として役立つち独学かつ短期間で狙える資格=FPと簿記に狙いを絞った
- キャリアの土台とするにはどちらも2級まで必要
- 「やると決めたらやり切る」という性格を強みに、勉強開始を決意した
転職や新しいことにチャレンジしようとしている方、資格に興味を持っている方、そして簿記やFPに迷っている方へ。
私の経験が「一歩踏み出すきっかけ」になれば嬉しいです。
次回は、実際にどのようにFPや簿記の勉強を進めていったのか、具体的な方法をお伝えしていきます。
20代専門の転職スカウトサービス【マイナビジョブ20’sスカウト】関連記事
【営業職必見】営業が取るべき資格まとめ|ジャンル別おすすめ資格と活かし方
簿記2級へ挑戦【前編】1か月合格を目指した3級挑戦と失敗からの再スタート
資格取得に動き出すまで|転職・キャリアアップを目指す人のための挑戦ストーリー
独学でFP2級に合格する方法 同年に簿記取得も視野に!~勉強時間・教材・進め方を公開~

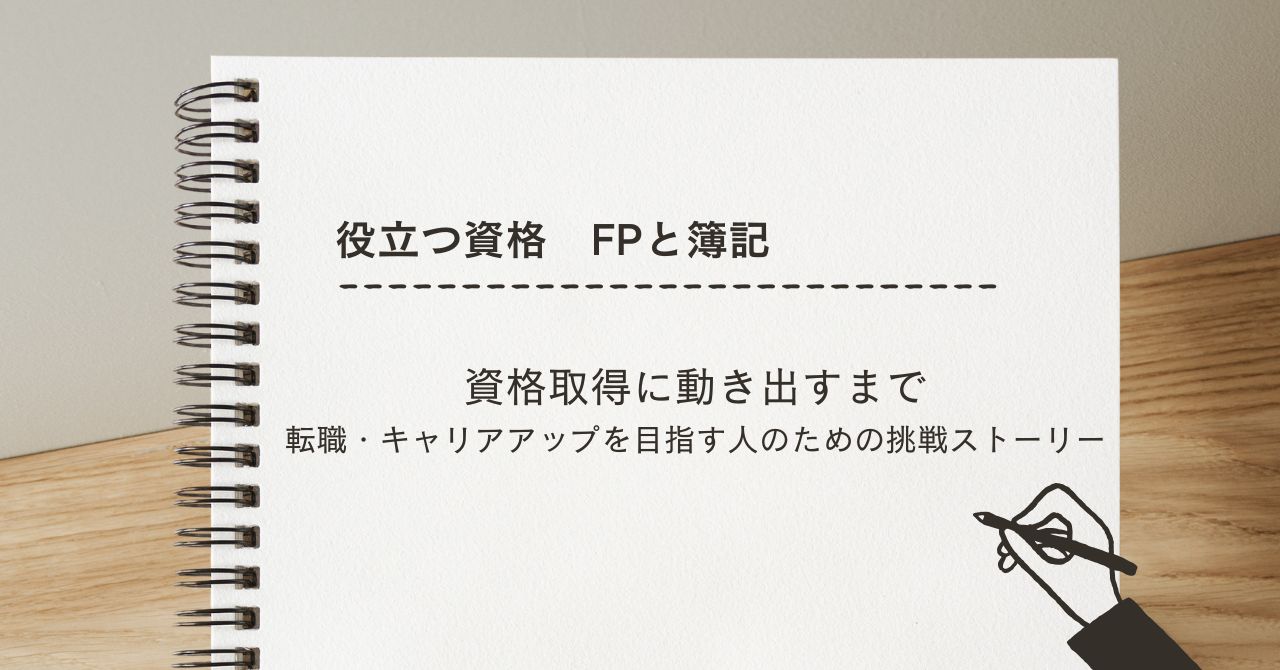

コメント